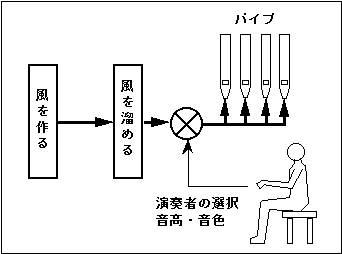
図3 オルガンの風の使い方
オルガンはなにより「風」を扱う「装置」です。その機能を図解すると下図のようになるでしょう。
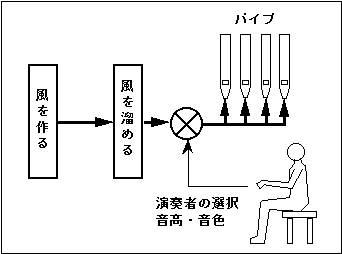
図3 オルガンの風の使い方
要するに、風を作って、一時溜めて、それを演奏者が選んだパイプに送り込むというのが、オルガンの機能と言うわけです。演奏者は、どんな高さの音をだすか、どんな音色の音を出すか(すなわちどの種類のパイプをならすか)を決めています。音の高さは鍵盤で、音色は「ストップ」というものを使って選択します。ストップについてはまた別項で扱います。
まず、風を作るのは「ふいご」"bellows","Balg","soufflet"です。最も古い形式のふいごは、木製の板を革のじゃばらでつないだもので、板の片側を蝶番で連結すると「くさび型」のふいごになります。このふいごの使われ方を描いた図が昔の本にあります。
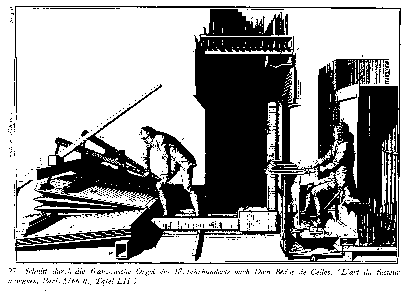
図4 ふいごの使い方
ダブルクリックすると大きな絵(GIF 70kB)が見られます。
(Dom Bedos de Celles "L'art du facteur d'orgues" [Paris 1776]より Fr.Jakob "Die Orgel" p51から転載)
他にもこんな絵があります。
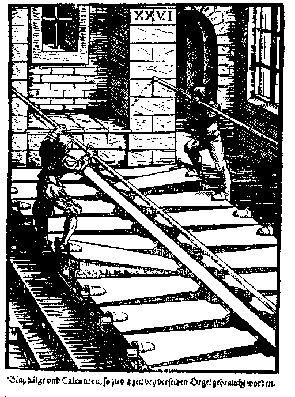
図5 ハルバーシュタットHalberstadtのオルガンのふいご
ダブルクリックすると、やや大きな絵(GIF 35kB)が見られます。
(Michael Praetorius "De Organographia" [Wolffenbuettel 1619]より Fr.Jakob "Die Orgel" p75から転載)
このように昔は人間がふいごを操作したわけで、美しい音楽の陰で一生懸命働く人もいたのですね。
バッハと同様、作曲よりオルガニストとして高名であったA.ブルックナーの弟は、このふいご職人 Kalkantでした。「兄貴がいくらえらいか知らないが、おいらがふいごを踏まないことにはなんにもできないんだぜ」とか言っていたそうです。ヨーロッパの地方の教会では、最近でも人力ふいごを使っているところがあり、礼拝のときにふいごを操るのは「良い子」の役目であったということが、NHK交響楽団のオーボエ奏者茂木大輔さんの本に、彼の師匠の思い出話として載っています。(「オーケストラは素敵だ」音楽之友社[1993])
人力のふいごはその後「箱ふいご」なるものに進化したあと、今では電動送風機にその座をゆずっています。しかし、電動送風機を使う場合でも、風圧を一定にするために途中にふいご状の「風溜め」を作るのが普通です。最近の楽器でもわざと人力ふいごを採用しているものもあります。
私の知る例は横浜のフェリス女学院大学にあって、人力ふいごによる演奏を聞いたことがあります。その時は、演奏後に、ふいごを操作した女子大生が紹介されて拍手を受けていました。:-)
ちなみにふいごを含めた送風装置は、どうしても騒音を発生してしまいます。どうやって送風機の音を抑えるか、は建造者の工夫のしどころです。かつてTelarcから出ていたMichael MurrayのCDに、演奏に使ったRoyal Albert Hall(?)の楽器についてMurray自身が語っている解説が収録されていましたが、その中で、送風機の騒音を実際に聴かせるという実験をしていました。
さらに余談を続けますと、オルガンの録音は教会で行われるものが多いわけですが、教会は専用の録音施設ではないので、内部外部の様々な「雑音」が不可抗力的に混入してしまうことがしばしばあります。鳥の声、自動車の通過音、地下鉄の音(!)、どこかのドアの閉まる音などなど。フランスのゴティークの教会は、会堂の内部空間が巨大かつ反響が豊かなためか、非常に低い振動数の共振音(?)がバックグラウンドノイズとして聞き取れることがあります。特にCDの時代になってからは目立つようになりました。そういえば、オルガンではありませんが、朝比奈隆さんが大阪フィルハーモニーを振って、オーストリアのザンクト・フローリアン修道院でおこなったブルックナーの第7交響曲の演奏会の録音には、第2楽章の終わった直後、絶妙のタイミングで修道院の時鐘がなりだしたのが収録されていて、朝比奈ファンは大喜び、なんていうのがありました。
次に、風を溜めるのは「風箱」"wind chest","Windlade","sommier"です。風箱は大抵、その上にパイプが並ぶように作られています。風箱は、風を溜めるだけではなく、溜めた風を演奏者が選んだパイプに送り込む機能も兼ねています。この、「演奏者が選んだパイプに送り込む」という仕組みが実はなかなか難しいのですね。長いオルガン建造の歴史のなかで、様々な方式が考案され評価されてきました。ここでは一応、最も優れた方式とされる「音高溝方式」"tone groove chest","Tonkanzellenlade"の「スライダーチェスト」"slider chest","Schleiflade","sommier a coulisses"なるものを説明します。
ちなみにオルガンには「建造する」という動詞をつかいます。英語でもbuild、ドイツ語でもbauen、フランス語ではconstruireを使うことが多いようです。もちろん「製作する」と
いうこともあります。
図3で示したように、演奏者がパイプを「選ぶ」行為には2種類有ります: どの高さの音を出すか、と、どの音色(ストップ)の音を出すか、です。ストップと音高を選べば、それに対応した1本(時に数本)のパイプが対応するわけですが、あるストップのある高さの音のパイプが鳴ってそれ以外の音が鳴らないようにするには、選んだストップと高さの音パイプ以外に風が通らないようにする必要があります。
すぐに思いつくのは、すべてのパイプそれぞれに専用の「弁」を設けて、そのパイプが選ばれたときだけ、専用の弁が開いて、風箱からの風が通るようにする方法です。しかし、これではパイプの本数が増えると開閉機構があんまり複雑になります。(近代になって電磁石を使った弁の開閉が可能になると、この方式がとられることがありました。)
そこでもう少し頭を使って、音高を選ぶ仕組みとストップを選ぶ仕組みを2段階にすることにします: 風箱を仕切って、まず一つの区画の中に風を送るかどうかの選択をする弁を設け、さらにその区画から個々のパイプへ風を送るかどうか選択する機構を設けるということにするわけです。風箱の区画を音高に対応させるか、音色に対応させるかで2通りの構成が可能ですが、現在では、音高に対応させる方が、音の響きや発音が優れているということにされているらしいです。(人によって意見が違う。) 風箱を仕切って作ったこの区画を「溝」とか「チャンネル」とか呼ぶことになっています。
一つの溝が一つの「音高」に対応するのが「音高溝方式」です。つまり、普通、音高は鍵盤を押すことによって選ぶので、ある鍵盤を押すとその音高に対応したチャンネルに風が入るようにしておくわけです。
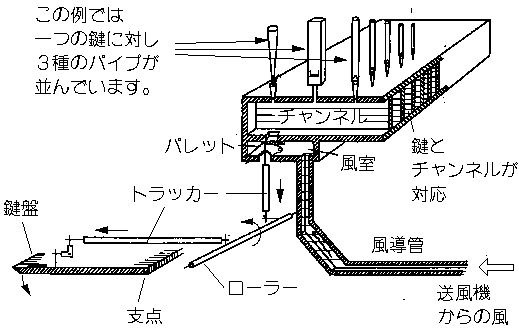
図6 音高溝(チャンネル)の仕組み
(H.クロッツ 「オルガンのすべて」 より改変して引用)
鍵盤が押されると、トラッカーとかローラーとか呼ばれる仕掛けが動いて、風室とチャンネルとの仕切りにあるパレットという小さな弁を開きます。風室には送風機からの風が風導管経由で送り込まれているので、パレットが開くと風室から風がチャンネルに通り、チャンネル上のパイプが鳴ります。チャンネルは鍵盤と1:1に対応していて、例えば54鍵の手鍵盤に対しては、風箱は54個のチャンネルに仕切られているわけです。一つのチャンネルの上に立っているパイプは皆同じ鍵に属していることになります。(必ずしも「同じ音」が出るパイプではありません。倍音管があるからです。)
では、チャンネルから音色を選ぶにはどうすればいいか。これにもいくつかの方法があるらしいのですが、ここで説明する「スライダーチェスト」は大変頭のいい方式です: 風箱の上面のパイプが立っている面の板を3重にします。各々の板に風箱からパイプへ風が通るように小さな穴をパイプの数だけ開けておきます。真ん中の板をチャンネルと直角方向に分割しておいて、各々独立にずらせるようにします。これをスライダーと呼びます。あるパイプの真下のスライダーは、それが正しい位置にあるときだけ上下の板と穴が一致して、風箱からパイプに風が通ります。一つのスライダーの真上に一つの音色に属するパイプを並べておけば、スライダーをずらすことによって、対応する音色のパイプすべてへの風の通りを制御できます。こう書いてもわかりにくいので、下の図をご覧ください。
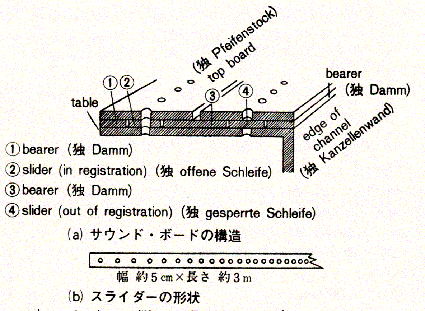
図7 スライダーの仕組み
(平島達司「オルガンの歴史とその原理」p29から転載: 原図 H.クロッツ 「オルガンのすべて」)
図7(a)の左側では、スライダーの穴が上下の板の穴と一致しているので、風がチャンネルからその上のパイプ(描いてない)に通りますが、右側はスライダーが図の紙面に直角な方向にややずれて(「スライド」して)いて、穴が一致しないため、風が通らなくなっています。(b)はスライダーを抜き出したものですが、図の右側に向かってだんだん穴の間隔が狭くなっているのは、この図では右側の方に高い音のパイプ、すなわち短くて細いパイプが載るように描いてあるからです。
実は大昔のオルガンはこういう仕組みを持っていなかったので、鍵を押すと、それに属するパイプが一斉に鳴ってしまいました。時代が下ると、必要のないパイプへの風を「止める」ことにより音色を選ぶ仕組みが考案されたのです。これが「ストップ」というわけです。日本語でも「音栓」という訳語が当てられています。ドイツ語では"Register"、フランス語では"jeu"といいます。
図6と図7を組み合わせると次の絵のようになります。
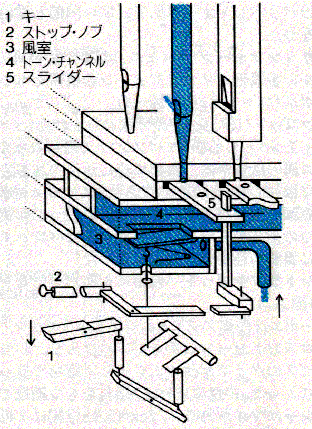
図8 スライダーチェスト全体構造
(カラー図解音楽事典(dtv-Atlas zur Musik) 白水社[1989] より引用)
大体おわかりいただけたでしょうか。説明する方も大変面倒くさいです。:-)
もう少しすてきな絵がオルガニスト松居直美さんのweb siteにあります。
スライダーを使う方式は大変古くからあったらしく、ハンガリーで発掘された、西暦228年の銘のあるオルガンの遺物には、すでにスライダー類似の機構が備わっているとのことです。スライダーチェストは、高精度な木工技術と良質の木材を必要とするため、19世紀にはいると次第に用いられなくなり、様々な「改良方式」にとって代わられましたが、今世紀になってその良さが再認識され広く採用されるようになりました。
ちょっと詳しいオルガンの解説書は、パイプの種類の記述と、この風箱の形式の記述に多くの頁を割いています。風箱の形式がなぜそんなに重要かというと、それはオルガンの「発音」の良し悪しを決定する基本的な要素だからです。演奏者がある鍵を押し下げたとき、どのように音が鳴り始めるか、は、音楽表現に大きな影響を与えます。風箱の形式と、鍵盤と風箱の間の「伝達」機構が、これらをほとんど決定してしまうのですね。伝達機構の方は後に述べようと思っていますが、執筆者の元気が無くて省略してしまうかもしれません。:-)
さて、オルガンのなかにおける風の用途はこれだけではありません。19世紀になるとオルガンの規模が大きくなり、鍵盤から風箱への距離が離れます。また、大きな音が好まれたのでオルガンの風の圧力が高くなります。このため、チャンネルへの風の通りを制御する弁を駆動するのに必要な力が大きくなり、鍵盤はとても重くなってしまいました。これを防ぐために、鍵盤と弁の間に空気圧を利用した補助動力装置を設けることが工夫されました。つまり、上で書いた「伝達機構」の「改良」です。これにも色々な方式がありますが、後の項で述べることにします。
その他に、オルガンに「ビブラート」をかける機構にもふれておくべきでしょう。伝統的に「トレムラント」"tremulant","Tremulant","tremblant"と呼ばれるこの機構は、要するに周期的に風箱への風圧を変化させるように動作します。色々な方式がありますが、多くはふいごから風箱への途中で周期的に風の一部を外へ抜くような仕組みになっています。
オルガンの風圧は時代や地域によって変化しました。風圧は、その圧力の空気が、管の中に押し上げることの出来る水の高さで表示する習慣になっています。バロック時代の楽器は、大体50-90mm程度の風圧でした。19世紀になると風圧は上昇して、100-120mm程度が普通になります。また、音色によって異なる風圧を用いることも可能になりました。バッハの森のオルガンは55mmという低い圧力の風を使っています。
さて、次回はいよいよお待ちかねのパイプの種類に関して説明しますが、これがもう大変フクザツで、どう整理して良いのか、困っています。まあ、気長にお待ちください。:-)
また、説明のわかりにくい点などあれば、ご遠慮無くmailでご質問ください。
| [ホーム] | [目次] | [前へ] | [次へ] |